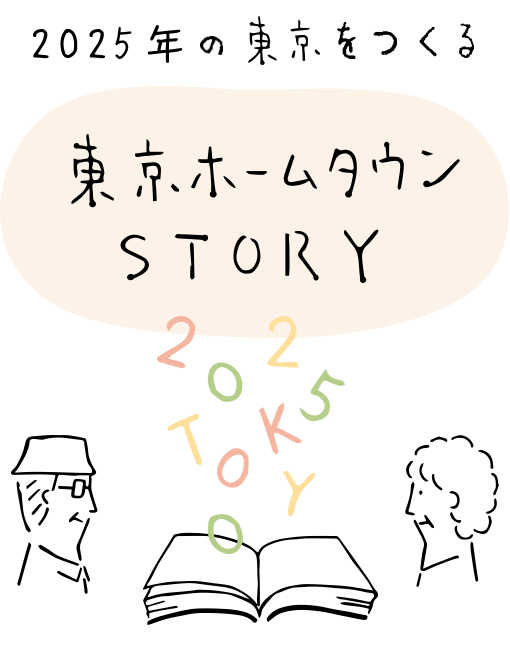東京ホームタウンSTORY
東京ホームタウン大学講義録
「東京ホームタウン大学2022」分科会レポート

都内の地域団体、プロボノワーカー等のみなさん
開催日:2022年2月18日(金)・19日(土)<br>会場:オンライン<br>動画:YouTubeの再生リストにリンク<br>●オープニングレポートはこちら<br>●メインセッションレポートはこちら
ページ:1 / 1
「東京ホームタウン大学」では、各テーマで活動する複数の団体からの事例発表や、初めての取り組みとなった社会人による地域研究活動「東京ホームタウン大学院」などの発表を基に、課題や解決策についてみなさんと共に考えていきました。その内容を以下にダイジェストでご紹介します。
分科会①(金曜夜の部)
地域参加の“きっかけ”の見つけ方
特技や趣味を活かしながら、地域福祉へとつながる活動を新たに立ち上げ、発展させている団体の方々に、活動立ち上げまでのストーリーや仲間探しのコツなどをお伺いしました。
●登壇者
- いにしえの会 林 久仁則さん
- こころとからだの元気Lab. 堀口 美智子さん
- Chiyoda Community Connection 川村 貴美江さん
- みんなのみたか 倉林 孝明さん
- ななテラス(NPO法人ドリームタウン) 佐々木 千恵美さん
●当日レポート
地域活動を実践されている登壇者のみなさんが感じてきた、地域とかかわることの価値について、そして、これから地域へ関わるにあたってのヒントについてお話しをいただきました。まずは興味の持ったところからスモールスタートすること、気軽に関わることからできることが広がっていくという具体的な事例についてお話しをいただき、視聴者の方々から多くの体験談をお寄せいただきました。
分科会②(以下、土曜昼の部)
いくつになっても参加したくなる居場所とは
高齢者から、社会人、子どもたちまで、人々が集いたくなる居場所とは?
コロナ禍での活動の工夫や、その中で感じられた活動の意義などを伺いながら、大都市東京ならではの「居場所」のあり方について考えました。
●登壇者
- けめカフェ 板井 佑介さん
- 調和SHC俱楽部 三浦 雅博さん
- 虹 橋爪 裕子さん
- 「私の思い出ノート」づくりの会 仁平 総さん
●当日レポート
コロナ禍のなかで活動を立ち上げ、または継続してきた4つの団体から活動の紹介がありました。各団体からは、コロナ禍での活動の工夫や、地域の「つながりの場」の大切さ、参加されている方々の生き生きとした様子が語られました。また、居場所とは、来る人は必ずしも目的を持っていなくてもよいものですが、そこに目的を持たせることで集まりやすい場になっていくことも見えてきました。
分科会③
安心して暮らせるまちをつくるには
ご近所同士で、あたりまえのように互いに助け合い、見守りあえる地域をつくりたい! 地域での模索を続ける活動者のみなさんの取組の事例から具体的な方法を学びました。
●登壇者
- 東邦自治会 片山 八彦さん
- 認知症みんなで考える中野ネットワーク「MIKAN」 伊藤 勝昭さん
- 三ツ藤木の葉の会 井上 ツヤ子さん
- 南町田福祉ネットワーク 三並 愛司さん
●当日レポート
地域の見守りや助け合いの活動をされている登壇者の方々から、高齢化が進行するまちが直面している課題とニーズ、そしてコロナ禍での活動の重要性と難しさをシェアしていきました。それらを乗り越えて地域のつながりづくりを進めていくための工夫と想いから、地域で暮らす私たちひとりひとりへ、地域でのアクションのヒントをいただきました。
分科会④
東京ホームタウン大学院「地域づくりの新しい視点」
これからの人生と地域を共に豊かにしていきたい研究生たちが、思い思いのテーマを設定し、約4か月をかけて実践的研究に挑んできました。分科会では、個性あふれる4つの研究の成果をプレゼンテーションしました。
●登壇者
- 地域で活動する人と地域の人々をつなぐインタビューメディアづくり 山口 亮さん
- 持続可能な地域活動・地域サービスとは?新たなビジネスモデルの可能性を調査 山田英二さん
- 身近な公園をハブとした、地域の“おたがいさま”を生み出す仕組みづくり 内山 千夏さん
- 誰もが立ち寄りやすいサロンとは?多様な地域の人が担う「居場所づくり」にむけた基礎調査 鈴木 利津子さん
- 落合・中井社会人大学院 野口 卓也さん
●当日レポート
現役世代から高齢世代まで、多様な世代で構成された4組の研究チームが、それぞれの実践研究の中から見えてきたことを発表しました。山口さんは、「地域で活動しているローカルプレイヤー」に焦点をあて、小平市を拠点にインタビューメディアづくりを実施。山田さんは、「持続可能な地域活動」をテーマに、事業継続のポイントや、活動参加のポイントを整理しました。内山さんは、公園の活用を「ちょっとやってみたい」気持ちを「ひと押し」するためのワークシートを成果物として作成。鈴木さんは、「いつでも・だれでもどうぞ」の居場所づくりを目指してオンラインサロンの試験的な実施やそこから見えてきたことを整理しました。 また、ご自身がプロボノ経験者であり、実際に地域活動団体も立ち上げた、地域活動実践の先輩でもある、落合・中井社会人大学院の野口さんにも登壇いただき、それぞれの取り組みに対して共感のコメントをいただきました。配信中はZoomのQ&A機能を用いた参加者同士の意見交換も盛り上がり、実際に参加者と登壇者がつながる場面も。他にも、アンケートでは「内容もアウトプットも素晴らしかった」「実践的なものに進化してきている印象を受けた」などのコメントもいただきました。
アフタートーク
いま、わたしたちにできること
イベントの締めくくりとして、2日間のプログラムで得た気づきを紹介するとともに、東京ホームタウンプロジェクトとして考える“東京のこれから” について総括しました。
●登壇者
- 広石 拓司 氏(株式会社エンパブリック)
- 嵯峨 生馬(認定NPO法人サービスグラント)
●当日レポート
「東京ホームタウン大学2022」でお届けしたプログラムで出たキーワード等を振り返りながら、これからの社会をどうみんなで一緒に作っていくか、地域参加の“入り口”のつくり方や、関わる人の輪の広げ方、人と関わる煩わしさを楽しみながらつながり続けていくことの大切さなどをあらためてディスカッションし、2日間の気付きを総括していきました。
-
 「地域参加のトビラ見本市」レポート
「地域参加のトビラ見本市」レポート
-
 「東京ホームタウン大学2024」分科会レポート
「東京ホームタウン大学2024」分科会レポート
-
 「東京ホームタウン大学2024」メインセッションレポート
「東京ホームタウン大学2024」メインセッションレポート
2025年、そして、その先へ。超高齢社会・東京のこれまでとこれから -
 【参加者の声】スキルに自信を持てた宝物のような経験。まちの見え方にも変化が
【参加者の声】スキルに自信を持てた宝物のような経験。まちの見え方にも変化が
-
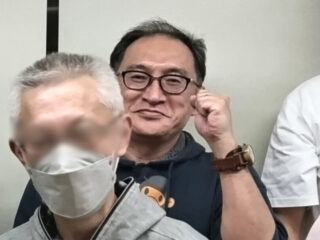 【参加者の声】異業種のチームメンバーから学び、楽しめたチャレンジ
【参加者の声】異業種のチームメンバーから学び、楽しめたチャレンジ
-
 【参加者の声】気軽に参加できて、新しい社会の一面も見られる機会に
【参加者の声】気軽に参加できて、新しい社会の一面も見られる機会に
-
 「東京ホームタウン大学2023」分科会レポート
「東京ホームタウン大学2023」分科会レポート
-
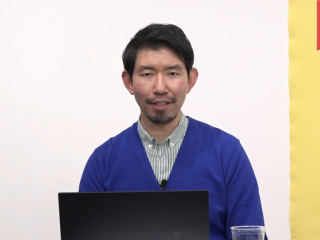 地域づくりの将来像を共有するために〜目標を言語化する方法
地域づくりの将来像を共有するために〜目標を言語化する方法
「東京ホームタウン大学2023」
基調講義レポート -
 楽しみながら支え合う〜心を動かす言葉の力
楽しみながら支え合う〜心を動かす言葉の力
「東京ホームタウン大学2023」
オープニングトークレポート -
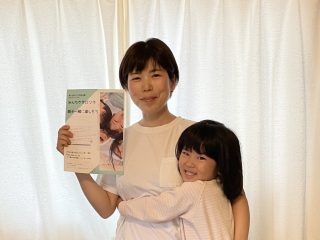 【参加者の声】団体さんへのリスペクト×私だからできること
【参加者の声】団体さんへのリスペクト×私だからできること